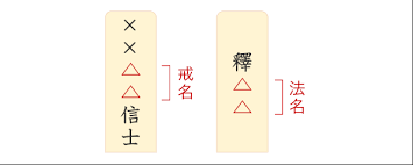
本日は法名(ほうみょう)と戒名(かいみょう)についてお話します。
「釋〇〇」や「釋尼〇〇」は「法名(ほうみょう)」と言い、浄土真宗で用います。「釋」の字は、お釈迦さまの「釈」を意味し、お釈迦様の弟子、仏弟子(ぶつでし)としての名のりを表しています。一方、「○○信士」や「○○信女」は「戒名(かいみょう」と言い、五戒(ごかい)や十戒(じっかい)など、定められた戒律を受けた者に付けられる名です。しかし、浄土真宗には受戒(じゅかい)はなく、僧俗の区別や身分、字数による階級の別もありません。すべては「釈」の名のもとに差異なく、共に仏弟子となるのです。法名は、ともすると亡くなられたときに付ける名前のように思われていますが、本来は「帰敬式(ききょうしき)」を受式して、生前にいただくものです。「帰敬式」のお問い合わせは寺までご一報いただければ幸いです。
次に浄土真宗では「戒名」を記した位牌は用いず、先祖代々の方の「法名」を掛軸(法名軸ほうみょうじく)にして、お内仏(おないぶつ)の側面にお掛けします。また、法名軸の代わりに、法名帳(過去帳)を置くこともあります。その法名の前に身を置く私達には、真の仏弟子となることが願われているのです。以上簡単ではありますが「法名」と「戒名」についてのお話でした。
合掌 釋昌信