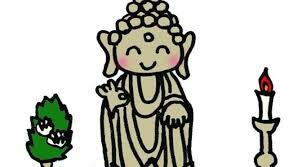
本日は「門徒(もんと)」という言い方についてお話します。浄土真宗では「檀家(だんか)」と言わずに「門徒(もんと)」といいます。一般的に寺にお墓を持つ方を「檀家(だんか)」といいますが、「檀家」はもともと梵語(ぼんご)[古代インドの言葉]の「ダーナ」という言葉に由来するものです。ダーナとは「布施(ふせ)」「めぐみをあたえる」を意味し、布施をする人・家を意味します。そこから「檀家(だんか)」という言葉が出てきたのです。江戸時代には幕府の宗教統制の一環として徹底された「寺請制度(てらうけせいど)」(檀家制度)により人々は特定の寺院に所属することを義務づけられていました。明治時代になりこの制度は廃止されましたが、現在でもその当時の名残で檀家という呼び名が用いられています。寺が今の役所の仕事をしていた事がうかがえますね。そこで浄土真宗ではなぜ「門徒(もんと)」なのか?
「門徒」とは、浄土門(じょうどもん)の徒輩(ともがら)という意味で、共にお念仏の教えに生きる人々のことを言います(浄土真宗でも「檀家」と呼んでいた時代もありました)。もともとは、広く、同じ門流(もんりゅう)に属して信仰を共にする人々を指して用いられていましたが、蓮如(れんにょ)さん(本願寺第8世)が「御文(おふみ)」(蓮如さんが門徒に向けて書いたお念仏の教えを伝えるお手紙)などで「門徒」という言葉を多く用いられ、本願寺が教団として大きく成長するにしたがい、おのずと浄土真宗をよりどころとする者の呼び名として使われ定着しました。現在では、浄土真宗の教えをいただく人を指す言葉として広く一般的に使われています。いわゆる、「布施」「めぐみをあたえる」人・家という役割の関係ではなく、共に歩んでいく関係である(御同朋・御同行)ということになります。寺は仏事の御縁(ごえん)でしかありえない関係という方が多くいらっしゃいますが、覺應寺に行くと何か面白いものがあるぞ!!という寺にしていければと思っております。今後とも「門徒」の皆様には御教授いただきますこと切にお願い申し上げまして本日は眠りにつきます。
合掌 釋昌信