住職のつぶやき 番外編(第二章)
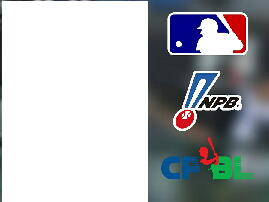
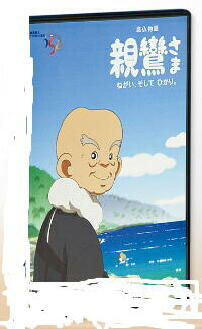
前回に続きます!
生きるヒントを得た。と最後にいいました。いろいろな場面で出てくるのが「親鸞を生きる」とか「自己とは何ぞや」とか難しい、そしてとっつきにくい言葉を並べるのが好きな教団だなと私は真宗の雰囲気を感じていました。本山(真宗本廟)や偉いと思っている住職方や何かと偉そうな感じがして私の肌には合わないな!と思っていて、親鸞さんが今の教団を見て何というかな?と漠然と感じています。「ざーんねーん!」と。越後から関東に移り、いわゆる庶民と親鸞さんが同座(同じ目線で)して一緒に酒を呑み馬鹿話をしながらともに歩んでいかれて京都に帰られたのです。だから鎌倉時代から今日まで真宗教団は発展してきたのだと理解しています。いわゆるわかりやすかったのです!以前にもお話しした「シンプル・イズ・ベスト」が本来親鸞さんが伝えていたことだとも理解してます。但しこの番外編では「脱マニュアル」ということを話しています。しかしこれは一つ間違うと「令和版 歎異抄」が生まれてしまうのです。わかりやすかったがために勝手に都合よく「脱マニュアル」をする人がいてそれを聞き広めてしまい「歎異抄」が生まれました。「異なることを歎く」ことになったのです。私はマニュアル(基本道)を否定しているわけではありません。現代社会においてはそれだけではどうにもならない場面が多いのでいろんな経験をもとにマニュアルから脱することを奨励しています。しかし、そんな中で親鸞さんはただ念仏のみ!南無阿弥陀仏!といってます。私は学生時代から「親鸞さんは本当に面倒なことをしてくれたわっ!」と心から思っていました。ですから「親鸞を生きる」とか「自己とは何ぞや」とか知らねえよ!と。しかし年月が過ぎ今考えると。
そうです、法(親鸞さん)を道標(みちしるべ)として歩み、道に迷ったら法(親鸞さん)に帰る。なんですね!でも、じつはこの表現は親鸞さんにチャレンジしています。
なぜかを朋に学んでいきましょう!
坊主も門徒も!「御同朋・御同行」です。つづく
合掌 釋昌信